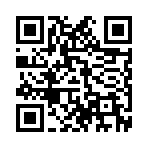2009年03月06日
NPOと行政の対話フォーラム’09に参加して!
NPOと行政の対話フォーラム’09」に参加してきました。
フォーラムの内容を、ちょっと報告します。
このフォーラムぬは、NPO・研究者・行政など全国から約200名の参加者があり、冒頭の主催者あいさつの中で、日本NPOセンターの山岡義典代表理事は、“『NPO』という言葉は、国の公益法人と区別された市民セクターとして、これまでは『特定非営利活動法人』を指すものととらえられてきた。
しかし、公益法人改革が進む中で、公益法人、さらには他の公共性ある法人、生協などの組合、任意団体まで、広く『非営利組織』ととらえる必要がある。”とのお話があり、まったくそのとおりであると思いました。
NPOと行政が対話し、対等なパートナーシップを組んでいくには、狭い意味でのNPO法人だけではなく、世の中で「公益のため、地域社会のため」という思いで活動しているすべての民間団体が、行政・企業とともに社会の課題を解決し、明るい将来を切り開く主体となるべきであると思います。
鼎談では、、自立支援センターふるさとの会理事の水田惠さん、川崎市長の阿部孝夫さん、前安孫子市長の福嶋浩彦さんの3人が登場され、様々な取り組みが紹介されました。
参加した第2分科会では、NPO法人市民活動情報センター代表理事の今瀬政司さんが、行政とNPOとのかかわりに関する実務的な提案として、“NPO等と行政の『協働契約書』”の提案をされました。
行政とNPOとの契約の形態には「委託」が多いが、現行の委託契約書では、
・事業主体は行政であり、NPOは事業を実施するが権利や主体性は限られ、下請けの立場である。
・NPOへの委託料に対する財・サービスの受益者は委託者としての行政であり、市民は行政を通じて、間接的にそのメリットを享受するような契約形態となっている。
・成果物等の権利(著作権等)が行政のみに帰属するようになっているため、その成果をNPOとして、今後の事業に十分生かせない。
こうした問題点を解決し、行政とNPOとの対等性やパートナーシップを実現するための条項を盛り込んだ、『協働契約書』を導入すべきであると。今後のあり方として、重要な視点の一つとなると思います。
この他、分科会では、三鷹市市民協働センターのセンター長・伊藤千恵子さんからの発表もあり、NPOとの「パートナーシップ協定」や「自治基本条例」、無作為抽出による「市民会議」といった、市民を巻き込んだまちづくりの事例が紹介され、三鷹市のパワーを感じました。
また、特に感銘を受けたのが、行政の立場から見た住民との関係として、安孫子市長時代に議会との間で、根回し抜きのオープンな議論を行ってこられた福嶋浩彦さんのお話でした。
“自立した自治体行政を確立するためには、主権者市民の意思に基づくことが必要である。自治体では、国政と異なり、議員だけでなく、首長も直接公選で選ばれている。地方自治は、選挙だけでなく、首長のリコール、議会の解散、条例制定、監査請求、住民訴訟など、住民が日常的に直接かかわるさまざまな権利が地方自治法上付与されている。 さらに、自治体によっては、自治基本条例が制定されるなど、さらに積極的な参加機会が設けられていることもある。”
“首長が住民との直接対話をすると、議会から「議会軽視だ」と声があがることがあるが、首長も住民から直接公選で選ばれている以上、議会だけでなく住民と直接対話していく責任がある。国政の場合には、内閣が国会に対してのみ責任を負う議院内閣制であるため、内閣が国民との対話を直接行おうとすれば「国会軽視」と言われるかもしれないが。”
国政と比べ、住民との関係の深い地方政治・行政について、制度的な裏付けを挙げており、わかりやすい説明であり、日常生活の中で見失っている社会基盤について、もう一度意識し、見つめな直す必要があるとに気がつきました。
以上、こんな内容でした。
各団体の皆さんのネットワークづくりや社会的意義について、勉強してみるいい機会です。
これからもお知らせしますので、皆さんも参加してみましょう。
フォーラムの内容を、ちょっと報告します。
このフォーラムぬは、NPO・研究者・行政など全国から約200名の参加者があり、冒頭の主催者あいさつの中で、日本NPOセンターの山岡義典代表理事は、“『NPO』という言葉は、国の公益法人と区別された市民セクターとして、これまでは『特定非営利活動法人』を指すものととらえられてきた。
しかし、公益法人改革が進む中で、公益法人、さらには他の公共性ある法人、生協などの組合、任意団体まで、広く『非営利組織』ととらえる必要がある。”とのお話があり、まったくそのとおりであると思いました。
NPOと行政が対話し、対等なパートナーシップを組んでいくには、狭い意味でのNPO法人だけではなく、世の中で「公益のため、地域社会のため」という思いで活動しているすべての民間団体が、行政・企業とともに社会の課題を解決し、明るい将来を切り開く主体となるべきであると思います。
鼎談では、、自立支援センターふるさとの会理事の水田惠さん、川崎市長の阿部孝夫さん、前安孫子市長の福嶋浩彦さんの3人が登場され、様々な取り組みが紹介されました。
参加した第2分科会では、NPO法人市民活動情報センター代表理事の今瀬政司さんが、行政とNPOとのかかわりに関する実務的な提案として、“NPO等と行政の『協働契約書』”の提案をされました。
行政とNPOとの契約の形態には「委託」が多いが、現行の委託契約書では、
・事業主体は行政であり、NPOは事業を実施するが権利や主体性は限られ、下請けの立場である。
・NPOへの委託料に対する財・サービスの受益者は委託者としての行政であり、市民は行政を通じて、間接的にそのメリットを享受するような契約形態となっている。
・成果物等の権利(著作権等)が行政のみに帰属するようになっているため、その成果をNPOとして、今後の事業に十分生かせない。
こうした問題点を解決し、行政とNPOとの対等性やパートナーシップを実現するための条項を盛り込んだ、『協働契約書』を導入すべきであると。今後のあり方として、重要な視点の一つとなると思います。
この他、分科会では、三鷹市市民協働センターのセンター長・伊藤千恵子さんからの発表もあり、NPOとの「パートナーシップ協定」や「自治基本条例」、無作為抽出による「市民会議」といった、市民を巻き込んだまちづくりの事例が紹介され、三鷹市のパワーを感じました。
また、特に感銘を受けたのが、行政の立場から見た住民との関係として、安孫子市長時代に議会との間で、根回し抜きのオープンな議論を行ってこられた福嶋浩彦さんのお話でした。
“自立した自治体行政を確立するためには、主権者市民の意思に基づくことが必要である。自治体では、国政と異なり、議員だけでなく、首長も直接公選で選ばれている。地方自治は、選挙だけでなく、首長のリコール、議会の解散、条例制定、監査請求、住民訴訟など、住民が日常的に直接かかわるさまざまな権利が地方自治法上付与されている。 さらに、自治体によっては、自治基本条例が制定されるなど、さらに積極的な参加機会が設けられていることもある。”
“首長が住民との直接対話をすると、議会から「議会軽視だ」と声があがることがあるが、首長も住民から直接公選で選ばれている以上、議会だけでなく住民と直接対話していく責任がある。国政の場合には、内閣が国会に対してのみ責任を負う議院内閣制であるため、内閣が国民との対話を直接行おうとすれば「国会軽視」と言われるかもしれないが。”
国政と比べ、住民との関係の深い地方政治・行政について、制度的な裏付けを挙げており、わかりやすい説明であり、日常生活の中で見失っている社会基盤について、もう一度意識し、見つめな直す必要があるとに気がつきました。
以上、こんな内容でした。
各団体の皆さんのネットワークづくりや社会的意義について、勉強してみるいい機会です。
これからもお知らせしますので、皆さんも参加してみましょう。
Posted by chiiki at 09:09│Comments(0)